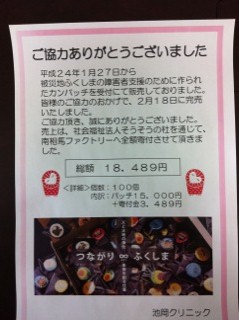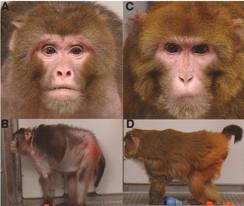昨日は校医をしているS中学の検診に行った。3年生、244名である。聴診器を入れている耳が痛くなり、続けて診察をするので滅多に凝らない肩が痛くなってくる。肉体労働である。
S中学は珍しくラグビー部のあるところで、神戸製鋼とかの結構有名どころのラグビー選手を多く輩出している。名門校である。
3年生のラグビー部員となるとおっさんだ。僕より体も大きくヒゲなんかもうっすら生えたりなんかしてさ。 女の子なんかも大人っぽくなってるし、検診って結構楽しいんじゃない?なんて言う人もいるがとてもそれどころではない。 午後診の時間は迫ってくるし、ガヤガヤやたらうるさい生徒諸君を並ばせるのに先生は声を張り上げるし、緊急の携帯は鳴るし、なんか気が遠くなってきた。
薄れ行く意識の中でぐるぐる変わる生徒諸君を診察しているうちに気がついたことがある。
僕よりおっさんに見えるボクも、不良予備軍の悪ぶってる彼も、おばちゃん?みたいな彼女も、一見年齢不詳かもしれないがみんな手が幼いのである。 手が子供。 つやが良く、血色がよく、プックリしている。細胞が若い。
手は年齢を表すというのはよく言われる。しわ、シミが加齢と主に増え、張りがなくなる。その変化は顔以上、特に男性は手に気を使わない分だけ著明に現れる。 昔知り合ったある男性は(奥さんがアメリカ人だった)、ふと気がつくと手が本当にきれいだった。そのことを指摘すると、彼はその当時男性は全く対象外だったエステに行っていると言った。「いや、嫁さんがね、営業職だったら見かけを絶対ちゃんとしなくちゃだめだって言うんですよ。で、つてをたどってね、月に1回、顔とか手とかやってもらってるんです。いやー、嬉しいなー、わかってもらえて」。 仕事で彼と知り合ったのだが、確かに彼はダントツで優秀であった。今頃どうしているかな。
手は実は病気もよく表す。貧血は爪をだめにするし、案外変形も多い。 診察の時、手を見ていたら患者さんが「先生、何見てんですか?」と言うので「手相」と言ったら「そうなんだ」と言われた。不徳の致すところである。
手は病気以上に生活環境が現れる。 余裕がないと手までまわらないもんね。女性は先刻ご存知だろうが。
手は脳の延長で、神経の先端が形になっていると思ってもいい。 ボケないためには「ばくちでもいいから手を使え!」という教えもあったな。 これからもっと手に注意をはらわなくっちゃ、と思っているうちに最後のボクが終わった。
つぼ、ってのもありましたね。